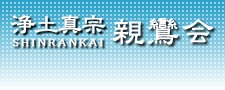亡き父母への真の孝行
「親鸞は父母の孝養のためとて念仏、一返にても申したることいまだ候わず」(歎異抄5章)
ここで「孝養」とは「追善供養」であり、死んだ人を幸福にすると信じられている行為をいいます。4歳で父を、8歳にして母を亡くされ、誰よりも両親を慕われていた聖人が、「父母の追善供養に念仏一遍、称えたことがない」と言われています。これは念仏に限らず仏事一切、含めてのことですから、「親鸞は亡き父母を喜ばせるために、念仏を称えたこともなければ、読経や法要、墓参りなど仏事は一度もしたことはない」との断言なのです。
「死者の一番のご馳走は読経だ」と、僧侶は平然と追善供養を勧めていますから、盛大に葬式をあげ、年忌法要や墓の管理を欠かさないことが、亡き親や先祖の喜ぶことだと当然視されています。それらの風習をおろそかにすれば、「親不孝」と謗られるでしょう。多くの人が世間体を気にし、法事に力を入れるので、葬式ビジネスは繁盛します。特に読経への布施は額が決まっていないので、坊主には都合のよい財源となっています。
しかし読経によって死者が救われるという考えは元来、仏教になかったのです。お経というのは、釈迦が生きた人を相手になされた説法を記したものであり、死人に聞かせるために説かれたものは一巻もありません。
平生に絶対の幸福に救われる教えこそ、真実の仏法であることを明らかにするために、親鸞聖人は衝撃的な告白で、世の根深い迷信を打破されたのです。
亡くなった親や先祖を大切に思うなら、それらの人が本当に望んでいることを知らねばなりません。子や孫である私たちが幸せになることこそ、最大の願いでしょう。だからまず、自分が真剣に阿弥陀仏の本願を聞き抜き、一日も早く絶対の幸福に救われなければなりません。この世で弥陀に救い摂られた人は、命終わると同時に、浄土に往って仏に生まれさせていただくことができます。仏に成れば自由自在に人々を救うことができることを、『歎異抄』第5章の末尾には、こう諭されています。
「ただ自力をすてて急ぎ浄土のさとりを開きなば、六道四生のあいだ、いずれの業苦に沈めりとも、神通方便をもってまず有縁を度すべきなり」
はやく弥陀の本願に救い摂られて絶対の幸福になり、この世の命が尽きて浄土で仏のさとりを開けば、どんな迷いの世界で苦しんでいる人でも、仏の不可思議な力で縁の深い人から救うことができるのです。
願わくは葬式法事を単なるしきたりに終わらせず、参列者が無常を念じて真剣に聞法し、親族も知人も一人残らず浄土で再会する勝縁にしたいものですね。
(R6.1.15)